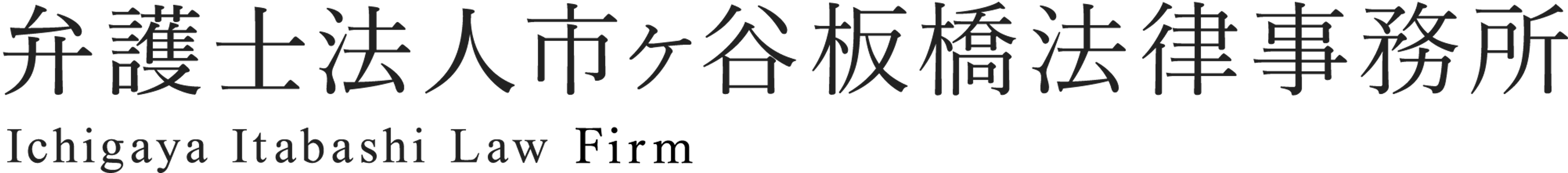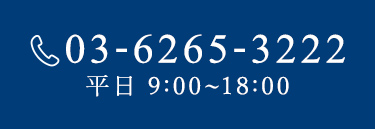2025/04/25 解決事例・コラム
【企業法務】事業承継と相続税対策|中小企業オーナーが今から取り組むべき3つのポイント
【事業承継と相続税対策】 中小企業オーナーが 今から取り組むべき3つのポイント
中小企業オーナーにとって、相続税対策は「いつかやればいい」では済まされない重要なテーマです。特に、ご自身に万が一のことがあった場合、会社の経営がストップし、ご家族も困るという事態が発生しかねません。
本コラムでは、「事業を安定的に継続させる」ことを最優先に考えた相続税対策について、当事務所が3つの重要ポイントを解説します。

1. 自社株式の承継が遅れると株主総会が開けない?事業承継リスク
中小企業では、オーナー経営者が自社株式を100%保有しているケースが多く見られます。この場合、経営者が急逝した際、その株式は相続人へ引き継がれることになります。しかし、経営に関与していないご家族(配偶者やお子さま)が株式を相続すると、以下のリスクが発生します。
-
株式の相続手続きが完了するまで、株主が確定しないため、株主総会を開催できない。
-
代表取締役の選任ができず、経営の意思決定が停止。
-
銀行取引や契約の更新などがストップし、会社の資金繰りが悪化する可能性。
-
複数の相続人が株式を分散相続した場合、経営方針に対立が生じ、事業継続が不安定になる。
これが、自社株承継を先送りする最大のリスクです。特に、中小企業では株式=経営権そのものであるため、株式を誰がどのように承継するかを早めに決めておく必要があります。
遺言書の作成や事業承継税制の活用を含め、円滑な株式承継と相続税対策を行うことで、こうしたリスクを回避できます。
2. 相続税評価額を抑える財産整理の工夫
相続税は、財産評価額が高いほど税負担が重くなります。そのため、相続税評価額を抑える財産整理が必要です。
例えば、現金や有価証券は市場価格がそのまま評価額となりますが、生命保険や不動産であれば、相続税評価額を抑えられる場合があります。特に生命保険は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となるため、現金を生命保険に切り替えることで節税効果が見込めます。
不動産投資も節税対策として活用できます。不動産は相続税評価額が市場価格より低く算定されるため、課税対象が減少します。ただし、不動産は流動性が低く、遺産分割が難しくなるリスクもあるため、慎重な判断が必要です。特に、マンション評価ルールの改正(2024年)により、相続税評価額が引き上げられた点にも留意しましょう。
3. 生前贈与と事業承継税制の活用
生前贈与は、相続税対策の基本手法の一つです。特に自社株式については、会社の利益が少ない時期や、役員退職金で利益を圧縮したタイミングで贈与すると、税負担を抑えられます。
また、2024年の税制改正により、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択が重要になっています。相続人以外への贈与や、7年以上生存見込みがある場合は暦年課税が適し、それ以外は相続時精算課税が有利とされています。
加えて、事業承継税制を活用することで、自社株式の贈与税や相続税が猶予・免除される可能性があります。ただし、この制度は要件や手続きが複雑なため、専門家と連携して進めることが不可欠です。特に、株式を複数人に分散相続させると経営権が不安定になるリスクもあるため、税金対策だけでなく事業の安定継続を第一に考える必要があります。
まとめ:相続税対策は早めの準備が鍵
中小企業オーナーにとって、相続税対策は事業継続のための最重要課題です。万が一の事態に備え、株主総会が開けないリスクや経営の停滞リスクを回避するためにも、早期の計画と準備が不可欠です。
当事務所では、事業承継や相続税対策について、税理士や司法書士と連携し、オーダーメイドのサポートをご提供しています。相続税評価額の見直しや生前贈与のプランニングなど、幅広いご相談に対応しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。