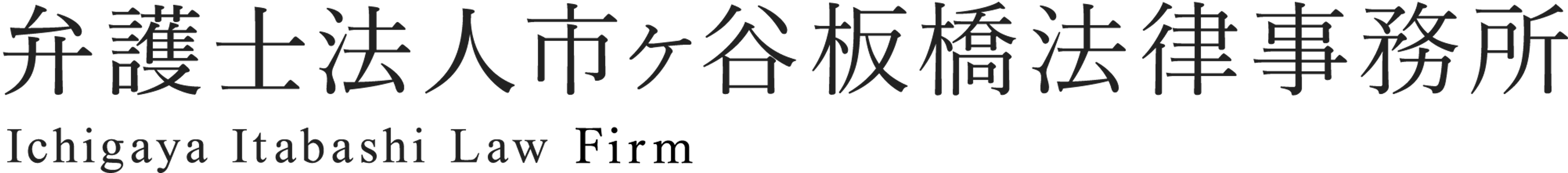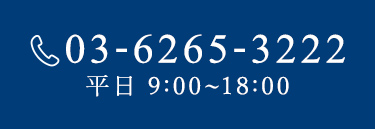2025/10/16 解決事例・コラム
建物の建替えと立退料:「正当事由」をやさしく解説
建物の建替えと立退料
:「正当事由」をやさしく解説
最終更新日:2025年10月16日(木)

1.建物が古くなったら、借主に立ち退いてもらえる?
長年貸している建物が老朽化し、「そろそろ建て替えたい」と考える大家さんは少なくありません。ただし、建替えを理由に契約更新を拒んだり、途中で打ち切ったりするには「正当の事由(以下正当事由と呼びます。)」が必要です(借地借家法28条)。
「正当事由」とは、大家さんの事情だけでなく、借主の暮らしや営業への影響も含めて総合的に判断する仕組みです。
この考え方のもとでは、たとえば、借主が長年暮らしていたり、その場所で事業を続けている場合は、安易に退去を求めることはできません。
2.「正当事由」は何を見て決まる?
裁判所は次のような点をまとめて見て判断します。どれか1つだけではなく、全体のバランスで決まります。
・大家さんと借主のどちらに、どの程度の「使用の必要性」があるか
・これまでの契約や使用の経過
・建物の状態(老朽化・安全性・耐震性など)
・立退料(財産上の給付)の提示があるか など
3.最近の傾向:建替え理由の明渡しは増えている?
令和期(2019年~2024年)の裁判例を集めた近年の調査、『借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書』では、明渡を求める理由として、建替え・取壊しは全体の約6割にのぼりました(87件/137件)。そのうち、そしてその約7割は正当事由として認められています。過去の同種調査と比べると、老朽化を理由に認められるケースは増加傾向といえます。
背景には、地震リスクへの意識の高まりや、耐震性不足の建物への対応が社会的課題になっていることが挙げられます。実際、多くの裁判例で耐震性の問題が重要な判断材料になっています。
4.耐震性能は大きな判断ポイント
耐震性に不安がある建物ほど、建替えの必要性は高く評価されやすい傾向にあります。とはいえ、耐震性に問題があるというだけで、直ちに明渡しが認められるわけではありません。
下記のような事情がある場合、建替えが認められないことがあります。
・補強工事で安全を確保できる(しかも費用が妥当)と評価される場合は、建替えの必要性が弱まる
・建替えの計画が具体的でない、あるいは立退料の提示が不十分だと、「正当事由なし」と判断されることがある
5.「建替えの必要性」と「建物を使う必要性」の違い
法律はもともと、大家さんと借主、それぞれの「建物を使う必要性」を比べる構造になっています。そのため、「建て替えたい」という希望(建替えの必要性)が、そのまま直ちに「建物を使う必要性」の高さを意味するわけではありません。
単に家賃収入を増やしたいといった経済的理由だけでは、正当事由は認められにくいのが実務です。一方で、老朽化や耐震性不足が深刻で、補強では安全や機能が保てず、費用対効果の面でも建替えが合理的といえる場合には、総合評価の中で大家さんの使用の必要性が高いと判断されやすくなります。
6.経済的合理性:修繕か、建替えか
判断の現場では、修繕・耐震補強にかかる費用と、建替えにかかる費用・効果が比較されます。改修しても長くもたないと見込まれる場合は、「建替えの方が合理的」と評価されやすくなります。この「経済的合理性」は、土地・建物を有効活用できているかという観点とも結びつき、総合評価に影響します。
7.立退料の役割
立退料は、バランス調整のための重要な要素です。建替えの必要性が高くても、借主への影響が大きいときは、適切な立退料の提示などでようやく正当事由が補われることがあります。
逆に、立退料の提示がない/著しく低いと、正当事由なしと判断される例が目立ちます。立退料には、引越費用だけでなく、営業の休止・移転に伴う損失や、生活基盤の再構築コストなど、実態に即した補償が含まれるのが一般的です。
8.借主側の事情
裁判では、借主の利用期間が長い、高齢、代替物件が見つけにくい、移転で顧客を失うおそれが大きい(事業用)といった事情があると、明渡しを認めにくくなる傾向があります。「正当事由」は大家さんだけの評価軸ではなく、借主の生活・営業の継続可能性が重く見られます。
9.実務での進め方
- 客観資料の整備
・耐震診断、劣化診断、建築士意見など、安全性・老朽化の根拠を用意。 - 計画の具体化
・概略ではなく、設計・スケジュール・資金計画など、実現性の裏づけを。 - 修繕 vs 建替えの費用対効果
・補強ではなく建替えのほうが経済的合理性を有することの証明。 - 立退料の設計
・生活・営業への影響を斟酌し、金額の妥当性を確保。 - 誠実なコミュニケーション
・借主の事情をよく聞き、移転先の紹介やスケジュール調整も含めて提案。
10.まとめ
安全性(耐震・老朽化)と経済的合理性が建替えの中核です。ただし結論は、借主の事情・立退料・計画の具体性などを総合して決まります。実務では、証拠の整備、実現可能な建替え計画、誠実な交渉が、解決の近道です。
「建替え」は社会的に必要な場面も多い一方で、生活・営業の基盤を守るという重要な視点も欠かせません。両者のバランスを取る道筋として、「正当事由」と「立退料」が機能している。これが現在の実務の姿です。
参考文献はこちら
公益社団法人商事法務研究会『借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書』(令和7年3月)
監修:秋山 靖浩(早稲田大学大学院法務研究科 教授)/ 執筆:梶谷 康久(東北学院大学 法学部 准教授)
https://www.moj.go.jp/content/001447355.pdf
ご相談のご案内
家族問題や不動産トラブルでお困りの方は、下記より面談・オンライン相談をご予約ください。状況整理から具体的な手続設計まで、弊所弁護士が丁寧にサポートいたします。