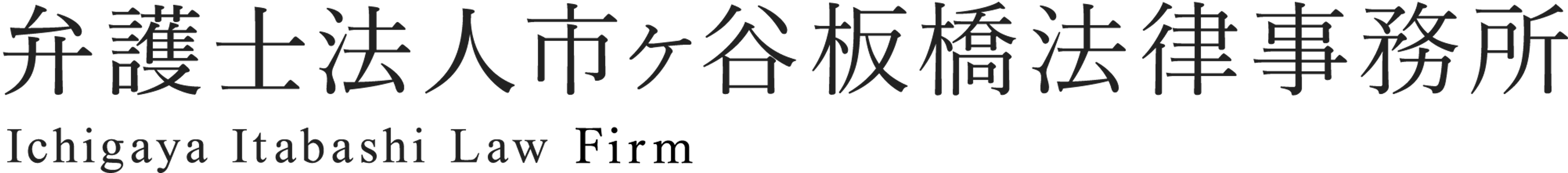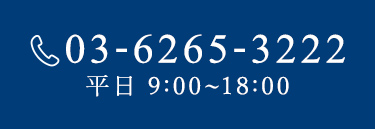2025/09/24 解決事例・コラム
墓じまいに伴う手続きと費用の実務 お寺が契約書を作成すべき理由
墓じまいに伴う手続きと費用の実務 お寺が契約書を作成すべき理由
最終更新日:2025年9月19日
はじめに
近年、少子高齢化やライフスタイルの変化により「墓じまい」を検討する家庭が増えています。墓じまいとは、既存のお墓を閉じ、遺骨を他の場所へ移す手続きのことを指します。
しかし実際に進めようとすると、寺院や檀家の間で費用負担や慣習に関する認識の違いからトラブルが発生することも少なくありません。特に、離檀料や閉眼供養に伴う費用は法律に明確な規定がなく、慣習的に請求されるため「なぜこの金額なのか」という疑問が檀家側に残りやすいのです。
そこで重要になるのが、寺院側による契約書や合意書の作成です。本稿では、墓じまいに必要な手続きや費用の実態、そして契約書を整備することで得られるメリットについて解説します。
墓じまいに必要な主な手続き
墓じまいは単なる引っ越しのように簡単には進みません。遺骨を動かすには、法律上も一定の手続きが必要です。代表的な流れを整理すると、次のようになります。
- 親族間での合意形成
墓じまいは親族全員に関わる重要な問題です。後々の争いを避けるため、あらかじめ親族全員の同意を得ておくことが大切です。 - 寺院への相談と了承
墓地を管理するお寺に墓じまいの意向を伝え、閉眼供養(魂抜き)の実施日程や費用を確認します。 - 改葬許可申請
遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合、市区町村役場で「改葬許可証」を取得する必要があります。 - 閉眼供養・撤去工事
僧侶による読経のもと閉眼供養を行い、その後、石材業者に依頼して墓石を撤去します。 - 遺骨の移転・再埋葬
改葬許可証に基づき、新しい墓地や納骨施設に遺骨を納めます。
費用の実態とよくある項目
墓じまいにかかる費用は地域や寺院ごとに差がありますが、一般的には以下のような項目があります。
- 閉眼供養のお布施:僧侶による儀式に伴う費用。数万円程度が多いですが、明確な基準はありません。
- 離檀料:檀家としての関係を終了する際に支払う謝礼。数十万円単位で請求される例もあります。
- 墓石撤去費用:石材業者に依頼する撤去工事費。墓の大きさや立地条件によって金額は大きく変動します。
- 過去の管理料精算:未納分の管理費用を清算するよう求められるケースがあります。
これらの費用には法律での定めがなく、多くは「慣習」や「お寺ごとの方針」に委ねられています。そのため、檀家側が「根拠が分からない」と感じて不満を抱き、トラブルに発展することがあるのです。
トラブル事例
- 離檀料として高額な請求を受けたが、具体的な根拠が示されない。
- 閉眼供養のお布施を支払ったにもかかわらず、追加費用を請求された。
- 費用の明細がなく、親族間で分担方法を巡って揉めた。
こうしたトラブルは檀家側だけでなく、お寺側にとっても信頼関係を損ねる大きなリスクとなります。
お寺が契約書を作成すべき理由
- 費用の透明化:契約書に費用項目と金額を明示すれば、疑念を減らせます。
- 双方の安心感:檀家側は事前に理解して進められ、お寺側も不当なクレームを受けにくくなります。
- トラブル防止:契約書が証拠として機能し、無用な紛争を防ぎます。
- お寺の信頼向上:透明性を重視した対応は、檀家や地域からの信頼を高めます。
弁護士に相談するメリット
契約書を作るにあたっては、慣習と法律のバランスを取ることが重要です。寺院の実情に合わせながら、法的に有効で、かつ不当な請求と誤解されない形を整える必要があります。
弁護士に相談すれば、
- 契約書に盛り込むべき必須事項
- 将来的に想定される紛争リスク
- 法律上の有効性を担保する文言
などを踏まえた文案を作成してもらえるため、安心して運用できます。
まとめ
墓じまいは、親族にとってもお寺にとっても重要な節目となる出来事です。しかし、費用が慣習に依存しているために誤解や不満が生じ、結果として信頼関係に傷がつくケースは少なくありません。
だからこそ、お寺側が契約書を作成し、費用や手続きを透明化することが不可欠です。弁護士のサポートを得て、トラブルを未然に防ぐ体制を整えることが、寺院の円滑な運営と檀家の安心につながるでしょう。
ご相談のご案内
家族問題でお困りの方は、下記より面談・オンライン相談をご予約ください。状況整理から具体的な手続設計まで、弊所弁護士が丁寧にサポートいたします。