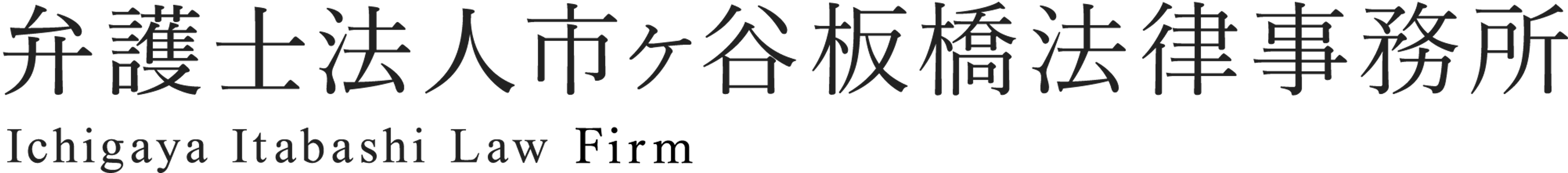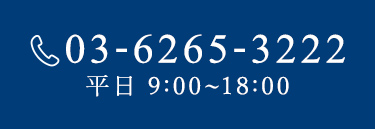2025/09/24 解決事例・コラム
離婚・面会交流・保護命令・夫婦関係の再生まで 統計と判例から読み解く家族問題
離婚・面会交流・保護命令・夫婦関係の再生まで 統計と判例から読み解く家族問題
最終更新日:2025年9月19日はじめに
夫婦や家族の問題は、生活の中で誰にでも起こり得る現実的なテーマです。離婚を検討する人もいれば、夫婦関係を修復したいと願う人もいます。さらに、離婚後も「子どもとの面会交流」「DVからの保護」「子どもの連れ去り防止」といった課題が残ります。本稿では、最新の司法統計や判例を交えながら、離婚・面会交流・保護命令・家族再生・子の連れ去り対策・夫婦のやり直しについて、一般の方にもわかりやすく解説します。
離婚の現状と方法
日本では離婚の約9割以上が協議離婚(夫婦の話し合いによる合意)で成立します。合意が難しい場合は、家庭裁判所での調停離婚、例外的に審判離婚、最終的には裁判離婚へと進みます。離婚は婚姻関係の終了にとどまらず、養育費・財産分与・慰謝料・親権といった現実的な問題を同時に整理する必要があります。合意書や調停調書に具体的かつ実行可能な取り決めを残すことが、後の紛争予防につながります。
面会交流 子どもの利益を最優先に
民法766条は、面会交流等の取決めにおいて「子の利益の最も優先」を明記しています。離婚後も親子関係は続き、親権のない親にも子どもと会う権利があります。現実には、子の拒否、同居親の消極姿勢、頻度や方法をめぐる対立が生じがちです。家庭裁判所は年齢・生活環境・DVの有無などを踏まえ、具体的な方法・頻度・連絡手段を定めることがあります。DV等の事情がある場合、判例上、面会交流を制限・不許可とするケースも存在します。
保護命令 DVからの避難手段
配偶者暴力防止法に基づく保護命令は、被害者の安全を確保するための強力な法的手段です。典型的には、接近禁止・住居や職場周辺への立入り禁止・電話やメール等の連絡禁止が命じられます。違反は刑事罰の対象となり、警察対応と連動します。安全確保のためには、避難先の確保、証拠(診断書・写真・メッセージ)の保存、相談窓口や弊所への早期相談が重要です。
家族再生 夫婦関係の修復に挑む
離婚以外の選択肢として、家庭裁判所の夫婦関係調整調停(円満調整)があります。令和5年の司法統計では、申立件数は1,811件、うち調停成立は503件(約28%)、同居継続に至ったものは137件にとどまります。成功率は高くはありませんが、第三者を交えた安全な対話の場が得られる意義は大きく、課題の見える化・合意できる範囲の明確化に役立ちます。民間のカウンセリングと併用する設計も有効です。
子の連れ去り対策 事前準備の重要性
別居開始時に一方の親が無断で子を連れ出す「子の連れ去り」は、親権・監護の争いに直結します。家庭裁判所には監護者指定や子の引渡し請求の手段がありますが、実務では現状維持が子の利益と判断される傾向があり、先に監護を開始した側が有利に働く場合があります。リスクを感じた段階で、証拠化・連絡記録の保存・保育園や学校との連携・迅速な申立て準備を進め、早期に専門家へ相談してください。
弁護士に相談するメリット
- 正確な法的評価:制度・判例に基づく現実的な選択肢を提示します。
- 交渉・手続の代理:感情的対立を避け、調停・審判・訴訟を適切に進めます。
- 子の利益の最大化:面会交流や監護での実務的合意案を設計します。
- 再発防止:実行可能な合意書・調停条項で将来紛争を予防します。
統計上、離婚関連調停では弁護士関与が一般的で、手続の見通し・必要資料・着地点が早期に明確になります。
まとめ
離婚・面会交流・保護命令・円満調停・連れ去り対策はいずれも家族の将来を左右します。統計や判例が示すとおり制度には限界や運用の幅がありますが、早期相談・証拠化・実効性ある合意設計でリスクは大きく減らせます。まずは状況の棚卸しから一緒に始めましょう。弊所は初回の方向けに、現状把握と優先順位づけのための相談枠をご用意しています。
ご相談のご案内
家族問題でお困りの方は、下記より面談・オンライン相談をご予約ください。状況整理から具体的な手続設計まで、弊所弁護士が丁寧にサポートいたします。