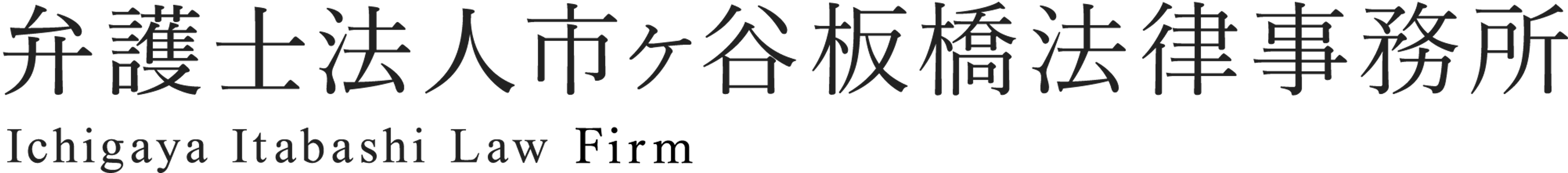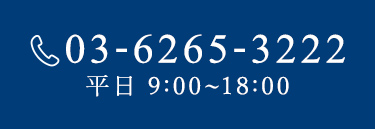2025/05/27 解決事例・コラム
【遺産相続】遺言に従うと財産が受け取れない?──「遺留分」で守られる最低限の相続権
「遺言書に“全財産を長男に相続させる”と書かれていたから、自分は何も受け取れないと思った」
そんなご相談を受けることがあります。ですが、たとえ遺言があっても、すべてがその通りになるとは限りません。
法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。この制度を正しく理解すれば、遺言によって一方的に財産を受け取れなくなるという誤解を解消できます。
本コラムでは、遺留分の基本と遺言書との関係について、よくあるご質問をもとに弁護士が解説します。

Q1. 「遺言書にすべての財産を○○に渡すと書かれていたら、私は何も受け取れないのですか?」
A. いいえ、遺留分があれば最低限の取り分を請求できます。
たとえ遺言書に「全財産を長男に」と記されていても、配偶者や子などの法定相続人には「遺留分」という最低限の財産を受け取る権利が保障されています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
Q2. 遺留分はどれくらいの割合で認められるのでしょうか?
A. 通常は法定相続分の1/2が遺留分とされます。
例えば、配偶者と子が相続人であれば、それぞれに法定相続分の1/2が遺留分となります。両親のみが相続人の場合は1/3が遺留分です。具体的な割合は家族構成によって異なりますが、相続財産全体に対して一定の金額が保護される仕組みです。
Q3. 遺留分の請求はどのように行うのですか?
A. 「遺留分侵害額請求」という手続きで金銭の支払いを求めます。
遺留分は基本的に「金銭」で回復されます。相続開始および遺留分を侵害する遺言や贈与の内容を知ってから1年以内に請求する必要があります。期間を過ぎると請求できないため注意が必要です。
Q4. どんな遺言が「遺留分」を侵害していると判断されますか?
A. 特定の相続人を極端に優遇するような内容の遺言です。
たとえば、再婚相手にすべての財産を渡す遺言や、生前贈与で長男にだけ大きな財産を移していた場合などが典型です。他の相続人が明らかに不利な状況に置かれるケースでは、遺留分が問題となる可能性が高いでしょう。
Q5. 遺留分をめぐるトラブルを防ぐにはどうすればいいですか?
A. 生前の対話と法的な対策が重要です。
具体的には、家庭裁判所の許可を得て遺留分放棄をしてもらう方法や、相続人が納得できるような遺言の作成、生命保険や預貯金での補填などが挙げられます。法的な視点からの助言を受けることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ:遺言書があっても、遺留分があれば財産を受け取れる可能性があります
「遺言書があるから何もできない」と思い込むのは早計です。法定相続人には、最低限の権利が法的に認められています。遺言内容に不安や疑問を感じた場合は、遺留分を含めた適正な相続を実現するためにも、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
弊所では、相続・遺留分に関する初回30分無料相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。