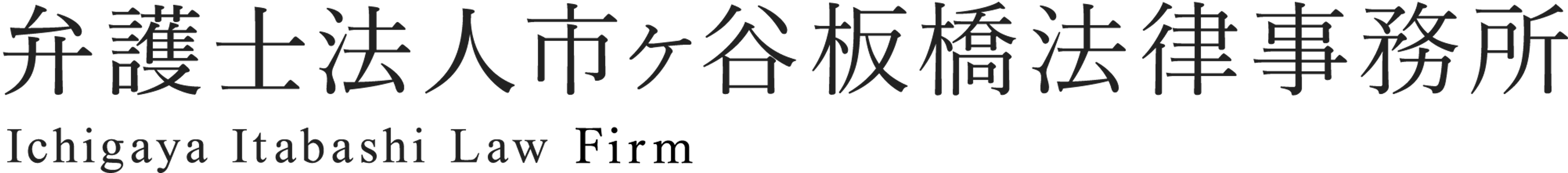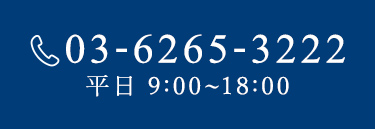2025/06/27 解決事例・コラム
【遺産相続】相続で取り分がなかった…それでもあきらめない「遺留分」とは?
【遺産相続】相続で取り分がなかった…それでもあきらめない「遺留分」とは?

相続に関するご相談で多いのが、「遺言書に自分の名前がなかった」「生前に兄だけが多くの財産を贈与されていた」といった、いわゆる“遺産の不公平な分配”にまつわる問題です。このようなケースでは、「自分にはもう何も相続できないのでは」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、民法はこうした不公平を是正するために「遺留分」という制度を設けています。遺留分とは、一定の相続人に対して保障される最低限の相続分のことを指し、被相続人が生前にどのような遺言や贈与をしていたとしても、この部分については法律によって守られています。
1.遺留分とは
遺留分は、被相続人の自由な財産処分と相続人の生活保障との調整を目的とした制度です。たとえば、遺言によって「全財産を長男に渡す」と記載されていた場合でも、他の子や配偶者は、民法に基づいて、一定の割合の財産を金銭で請求することができます。
遺留分が認められているのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、または子がいない場合の親や祖父母といった直系尊属に限られます。一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利が認められていないため、たとえ法定相続人であっても、遺留分を主張することはできません。
2.遺留分はどうやって取得する
遺留分は、自動的に与えられる権利ではなく、自ら権利を主張しなければ取得することができません。つまり、遺留分に相当する取り分を確保するには、遺産を多く取得している人に対して、「遺留分が侵害されている」として請求を行う必要があります。
この請求方法は、「遺留分侵害額請求」と呼ばれており、侵害された遺留分に相当する金額の支払いを求める制度です。請求された側が話し合いに応じ、合意が得られれば和解や合意書の作成で解決できますが、場合によっては調停や訴訟に進む必要があります。
3.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
2019年7月に民法が改正されるまでは、「遺留分減殺請求」という制度が使われていました。これは、遺留分を侵害している相続や贈与について、現物の財産そのものを取り戻すことを目的とした制度でした。不動産などの財産を共有状態に戻すことができましたが、それによって相続人同士の新たな紛争が生じることも少なくありませんでした。
これに対して、改正民法では「遺留分侵害額請求」という制度に切り替わり、遺留分に相当する金額を金銭で精算するという仕組みに変わりました。これにより、財産の共有状態が発生しにくくなり、より円滑な解決が期待できるようになりました。
4.遺留分の計算方法
遺留分を計算するには、まず被相続人が亡くなった時点での遺産総額を把握する必要があります。この遺産総額には、現金や預貯金、不動産、有価証券などの資産に加え、相続開始前の一定の生前贈与も含まれます。ただし、生前贈与については、原則として相続開始前10年以内のものが対象とされています。また、被相続人の借金や未払債務などのマイナス財産は差し引かれます。
次に、相続人の組み合わせに応じた遺留分割合を掛けます。子どものみが相続人である場合や、配偶者がいる場合は、遺産全体の2分の1が遺留分の総額となります。直系尊属のみが相続人である場合は、遺産全体の3分の1が遺留分の総額となります。
この総額を、各相続人の法定相続分に応じて配分したものが、個別の遺留分となります。たとえば、遺産総額が6,000万円で、子どもが3人いる場合、遺留分総額は3,000万円となり、それを3人で等しく分けると、各人の遺留分は1,000万円となります。
5.遺留分侵害額請求の手続き
遺留分侵害額を請求する際には、まず侵害している相手に対して意思表示を行う必要があります。この意思表示は、後日の証拠とするため、内容証明郵便など記録に残る方法で行うことが推奨されます。
請求の意思が相手に伝わったあと、当事者間での話し合いによって解決が図られる場合もありますが、合意に至らないときには、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになります。調停でも解決できない場合には、訴訟手続きに進み、最終的には裁判所の判断に委ねることになります。
なお、裁判では、遺留分の侵害があったこと、遺産の内容、相続人の構成、計算方法などを具体的な証拠によって立証しなければなりません。そのため、専門家のサポートを受けながら準備を進めることが望まれます。
6.遺留分請求の注意点|消滅時効と除斥期間
遺留分請求には時効があります。具体的には、相続が開始し、かつ自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内に請求しなければなりません。また、被相続人の死亡から10年が経過すると、たとえ侵害に気づいていなかったとしても、遺留分の請求権自体が消滅してしまいます。これを除斥期間といいます。
時効や除斥期間を過ぎると、正当な権利であっても請求が認められなくなるため、遺産分割に違和感や疑問を感じたら、速やかに弁護士などの専門家に相談することが重要です。
7.法定相続分との違い
遺留分と似た言葉に「法定相続分」がありますが、両者は異なる性質を持っています。法定相続分とは、遺言がなかった場合に民法上のルールに従って分割される相続割合を意味します。一方、遺留分は、遺言が存在していても、あるいは贈与によって不公平な分配がされていた場合でも、最低限保障される取り分を意味します。
また、法定相続分は自動的に適用されますが、遺留分は自分で請求をしなければ得ることができません。この点において、遺留分は“受動的にもらえるもの”ではなく、“能動的に取り戻すもの”という性質を持っています。
まとめ
遺言があるからといって、すべてを諦める必要はありません。民法には、特定の相続人に最低限の財産を保障する遺留分制度があり、この制度によって、相続の不公平を是正することができます。ただし、遺留分を取り戻すためには、自ら意思を示し、正しい手続きを踏む必要があります。
相続や遺産分割に不安を感じたら、まずは自分が遺留分権利者に該当するか、そしてどれだけの請求が可能かを確認しましょう。そのうえで、時効が来る前に必要な対応をとることが大切です。
弊所では、初回30分無料相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。