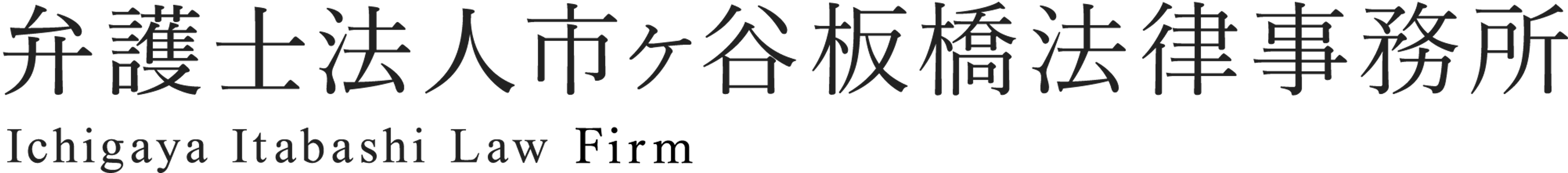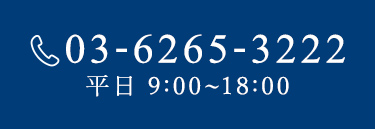2025/05/02 解決事例・コラム
【離婚】離婚と財産分与:夫婦の資産をめぐる法的整理の基本
市ヶ谷板橋法律事務所は、豊富な経験と実績に基づき、財産分与・親権・養育費・婚姻費用・不貞行為など、離婚にまつわるあらゆる法的課題に対応してきました。
協議離婚から調停・訴訟に至るまで、当事務所は一貫してサポートしています。

離婚に伴う財産分与は、夫婦の経済的な清算の場面であり、複雑で専門的な判断が必要となる重要な手続です。本コラムでは、財産分与の基本的な仕組みを中心に、法的ポイントをわかりやすく解説します。
【財産分与とは】
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)を離婚時に分け合う制度です。民法第768条に基づき、以下の3種類に分類されます。
-
清算的財産分与:最も一般的な形式で、夫婦で形成した共有財産を清算し、原則2分の1ずつ分与する考え方。
-
扶養的財産分与:一方の生活能力が著しく低い場合に、生活補助的に支払われるもの。
-
慰謝料的財産分与:有責配偶者に対して慰謝料を加味して支払う形式。
【共有財産と特有財産の違い】
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であり、対象は預貯金、不動産、有価証券、退職金、事業収益など多岐にわたります。一方、婚姻前から保有していた財産や、婚姻中でも一方が単独で相続や贈与を受けた財産は「特有財産」とされ、分与の対象外となるのが原則です。
ただし、特有財産と主張するには、証明資料の整備が不可欠です。預金の混同や名義変更の有無などにより、特有財産であることが否定されるケースもあります。
【2分の1ルールとその修正】
実務では「財産は夫婦の協力によって築かれた」との前提から、基本的に2分の1ずつ分与する「2分の1ルール」が用いられます。しかし、医師や経営者、スポーツ選手のように、専門技能や努力による高額収入を得ている場合、その寄与度を考慮して分与割合が修正されることがあります。
実際の裁判例でも、資産形成への配偶者の関与が薄いと判断された場合に、財産分与が5%〜40%程度にまで抑えられたケースも存在します。
【まとめ】
財産分与は単なる「分け合い」ではなく、夫婦関係の清算と新たな生活の出発を支える重要な法的手続きです。財産の種類や取得経緯、形成過程での寄与度などを精緻に分析し、適切な分与を設計することが求められます。高額資産の分与においては、専門家の助言を受けながら戦略的に対応していくことが不可欠です。
弊所では初回30分無料相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。