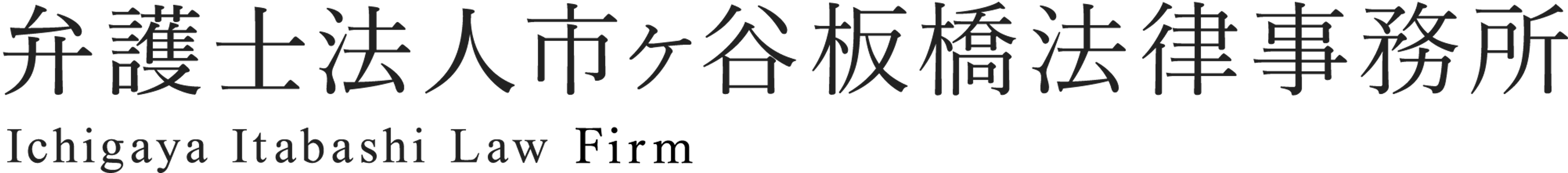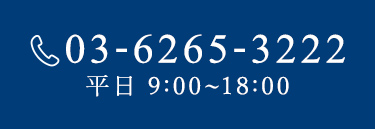2025/09/09 解決事例・コラム
別居中の生活費をどう請求する?婚姻費用の金額・始期・証明方法をわかりやすく解説
別居中の生活費をどう請求する?婚姻費用の金額・始期・証明方法をわかりやすく解説
最終更新日:2025年9月9日はじめに
夫婦が一緒に暮らすためには、食費や住居費、光熱費、子どもの教育費など、さまざまな費用が必要です。これらの「生活費」は、法律上では「婚姻費用(こんいんひよう)」と呼ばれています。
婚姻費用は、結婚している夫婦が共同生活を送るために必要なお金を、お互いに協力して出し合うという考えに基づいています。そしてこの費用は、夫婦が別々に暮らしている場合でも、離婚が成立していなければ分担し続ける義務があります。
本記事では、婚姻費用とは何か、どんな費用が対象になるのか、いつからいつまで支払う必要があるのか、金額はどうやって決まるのか、資料がない場合の対応まで、気になるポイントをわかりやすく解説します。
婚姻費用とは何か?
婚姻費用とは、結婚している夫婦が家庭生活を維持していくうえで必要な出費全体を指します。法律用語ではありますが、簡単にいえば「生活に必要なお金」のことです。
たとえば、食事や住居費、光熱費、通信費、保険料、医療費、子どもの教育費や保育料、通学交通費などが含まれます。日々の暮らしに必要な出費を思い浮かべていただければ、ほとんどが婚姻費用の対象になると考えてよいでしょう。
民法第752条は、夫婦には「互いに協力し助け合う(扶助)義務」があると定め、民法第760条は、収入や資産、その他の事情をふまえて婚姻費用を分担すべきことを定めています。つまり生活費は、どちらか一方だけが負担するのではなく、経済状況に応じてバランスよく分け合うのがルールです。
このルールは、夫婦が別居していても離婚が成立するまでは変わりません。別居中であっても、収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者に対して生活費を支払う必要があります。
婚姻費用に含まれるもの
婚姻費用に含まれるのは、「同居していたときと同じくらいの生活レベルを維持するために必要なお金」です。具体例は次のとおりです。
- 食費、家賃・住宅ローン、光熱費、通信費などの日常的な生活費
- 子どもの保育料・学費、通学交通費、習い事、制服代、給食費などの教育関連費
- 交通費、娯楽費や交際費
- 医療費、保険料、老後の備え(積立や年金)など
たとえば、子どもが続けている習い事の費用も、婚姻費用に含めて請求できることがあります。妊娠・療養など特別な事情がある場合には、医療費や通院費が加味されることもあります。
婚姻費用の支払いはいつから始まる?
婚姻費用は、相手に「支払ってください」と請求した月から発生します。代表例は次のとおりです。
- 家庭裁判所に「婚姻費用分担調停(または審判)」を申し立てた月
- 内容証明郵便などで、婚姻費用を請求したことが明らかな月
請求していない期間について、原則として大きく遡って支払ってもらうことは難しい点に注意が必要です。婚姻費用は「毎月の生活費」ですから、請求は原則として「1か月」単位で扱われます。
婚姻費用の支払義務はいつまで続く?
婚姻費用を支払う義務がなくなるのは、次のような場合です。
- 夫婦が正式に離婚したとき
- 別居をやめて、再び同居生活に戻ったとき
つまり、婚姻関係が続いている限り、そして別々に暮らしている限りは、原則として支払義務は継続します。「離婚が成立するまでの生活費」と考えると分かりやすいでしょう。
婚姻費用を証明するには?
金額を決めるには、夫婦それぞれの収入が重要です。まずは次のような「収入資料」を用意しましょう。
① 収入資料
- 給与所得者:源泉徴収票(直近前年分)
- 自営業者:確定申告書(直近前年分)
- 年金生活者:年金振込通知書
② 加算要素となる費用の資料
- 子どもの学校・保育園の領収書や請求書(学費・保育料・習い事など)
- 医療費の領収書や明細
- 家賃や住宅ローンの支払い明細
「何を・どれくらい支出しているのか」が分かる資料が多いほど、話し合いや手続がスムーズに進みます。
義務者が収入資料を出さない場合は?
「婚姻費用を計算するために、相手の収入が分からない…」というケースは少なくありません。相手(義務者)が資料を出さない場合でも、収入を推測する方法はいくつかあります。
-
住民票が同じままの場合
別居していても住民票が同じ世帯のままであれば、市区町村役場で「所得証明書(課税証明書)」を取ることができ、相手の収入を立証することができます。 -
裁判所に調べてもらう方法
役所や勤務先に対して、裁判所から「収入を教えてください」と照会してもらう「調査嘱託」という制度があります。ただし、守秘義務を理由に情報が提供されないこともある点には注意が必要です。 -
平均的な収入で推定する方法
どうしても分からないときは、厚生労働省が公表している「賃金センサス」という統計資料を使って、年齢・性別・職業ごとの平均収入から推定する方法もあります。ただし、この場合は実際より低めに出てしまうこともあります。
婚姻費用はどうやって計算する?
婚姻費用の金額は、家庭裁判所などが用いる「算定表(さんていひょう)」で計算するのが一般的です。夫婦それぞれの年収、子どもの人数・年齢などを当てはめると、標準的な金額の目安が分かります。
1.権利者・義務者の年収、子どもの人数・年齢に応じた表を選ぶ
2.条件を当てはめて、月額の婚姻費用を見積もる
算定表は、東京・大阪家庭裁判所が公表しており、インターネットでも確認できます。必要な条件が揃えば、ご自身でもおおよその目安を把握できますが、個別事情で増減することもあるため、正確な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
まとめ
婚姻費用は、別居中の生活を守るための大切なお金です。請求できる時期や金額は、請求のタイミングや資料の有無によって変わります。まずは早めに請求し、必要資料をそろえることが大切です。
「どこまで請求できる?」「証拠が足りないかも?」といった不安があれば、早めに専門家へご相談ください。状況に合った方法を一緒に検討できます。
📌 離婚前の生活費についてお悩みの方へ
婚姻費用の請求や調停手続は、弁護士に相談することでスムーズに進められます。
婚姻費用の相談を予約する