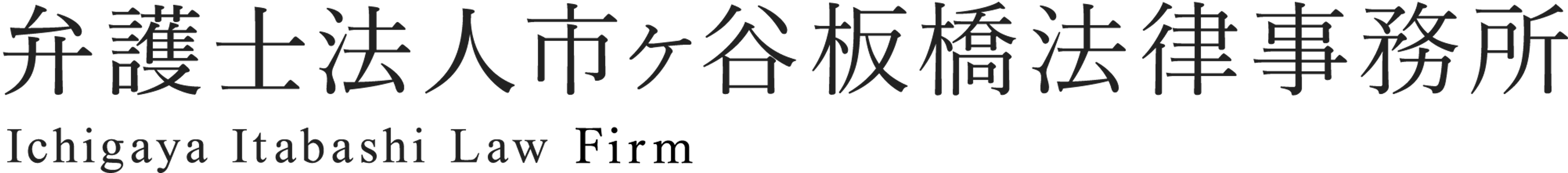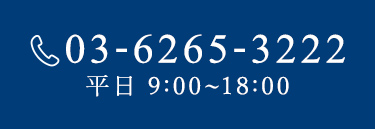2025/09/02 解決事例・コラム
退職合意書に盛り込むべき重要条項 ― トラブルを避けるための実務ポイント
退職合意書に盛り込むべき重要条項 ― トラブルを避けるための実務ポイント
最終更新日: 2025年9月2日はじめに
企業が従業員に対して退職勧奨を行い、合意に至った場合に取り交わされるのが「退職合意書」です。この書面は、退職条件を明確にし、後日の紛争を防ぐために非常に重要な役割を果たします。条項の不備があると、未払賃金や損害賠償請求などの追加トラブルに発展することも少なくありません。本稿では、退職合意書に必ず盛り込むべき基本条項と、事案に応じて検討すべき追加条項について解説します。
必ず盛り込むべき条項
退職合意書には、どのようなケースでも欠かせない基本的な条項が存在します。特に以下の2つは必須です。
① 退職・退職日・退職事由に関する条項
当事者間で退職が合意に基づいて成立すること、具体的な退職日、退職事由(例:会社都合)を明確に定める必要があります。
文例:「甲と乙は、甲が、乙を令和○年○月○日付で、会社都合により合意退職することを相互に確認する。」
② 包括清算条項
合意書に定めた内容以外には債権債務が存在しないことを確認し、後の追加請求を防ぐ条項です。「本件に関し」といった限定的表現を避けることが重要です。
文例:「甲と乙は、甲乙間には、本件合意に定めるもののほか、名称の如何を問わず、他に何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。」
事案に応じて検討すべき条項
個別の事情に応じて追加を検討すべき条項は以下のとおりです。
① 退職日までの労務提供免除条項
従業員が在籍しながら転職活動を行いたい場合に有効です。
文例:「乙は、令和○年○月○日以降第1項の退職日までの間の甲の労務提供義務を免除する。」
② 解決金支払い条項
退職に応じる条件として、解決金や特別退職金を支給する場合に盛り込みます。
文例:「乙は、甲に対し、令和○年○月○日限り、解決金○円を甲指定給与振込先口座に支払う。」
③ 給与支払い条項
退職日までの給与支払いを明確化し、包括清算条項との矛盾を避けるために必要です。
文例:「乙は、甲に対し、前項の退職日までの間に生じた月例賃金を、法定控除のうえ、各月の給与支払日限り、給与振込先口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。」
④ 守秘義務条項
他の従業員への波及を防ぐため、合意内容や経緯を第三者に漏らさないことを定めます。ただし従業員の強い反発が予想される場合は除外することもあります。
文例:「甲と乙は、本件合意の内容及び本件合意に至る経緯について、正当な理由がある場合を除き第三者に口外せず、本件合意書の第三者への開示を行わない。」
⑤ 在職中に知り得た情報に関する秘密保持条項
退職後も会社の機密情報を保持しないことを誓約させる条項です。
文例:「甲は、退職後も乙で知り得た機密事項、情報を外部に口外しないことを誓約する。」
「甲は、乙の業務に関する一切の情報を令和○年○月○日までに乙の指定する方法により乙に返却し、令和○年○月○日の翌日以降は乙の業務に関する一切の情報を保有しないことを誓約する。」
⑥ 代表者個人も含めた包括清算条項
ハラスメントなどが争点の場合、代表者個人への請求を防ぐために必要です。
文例:「甲、乙及び丙は、甲乙間及び甲丙間において、本件合意に定めるもののほか、名称の如何を問わず、他に何らの債権債務の存在しないことを相互に確認する。」
⑦ 物品返還条項
貸与物(PC・携帯電話・制服など)の返却を確実にさせるための条項です。
文例:「甲は、令和○年○月○日限り、乙から貸与を受けている物品一式を乙の指定する方法により返却する。」
⑧ 有給休暇買取条項
未消化の有給休暇を買い取る合意をした場合、その内容を明記します。
文例:「甲が退職日時点において未消化の有給休暇を保有している場合(令和○年○月○日時点では○日)、乙は甲に対し、有給休暇1日あたり○円で算出した金額を、退職日から14日以内に、給与振込先口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。」
まとめ
退職合意書は、退職の円満な成立と後日のトラブル防止に直結する重要な書面です。必須条項として退職条件と包括清算条項を明確に定めた上で、事案ごとに適切な追加条項を検討することが不可欠です。弊所では、退職勧奨や退職合意書の作成に関するご相談を随時承っております。実務経験豊富な弁護士が、御社の状況に即した最適なサポートを提供いたします。
退職合意書の作成にお悩みですか?
退職合意書の条項一つで、後日の紛争リスクは大きく変わります。専門的な視点でのチェックや起案が必要な場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。