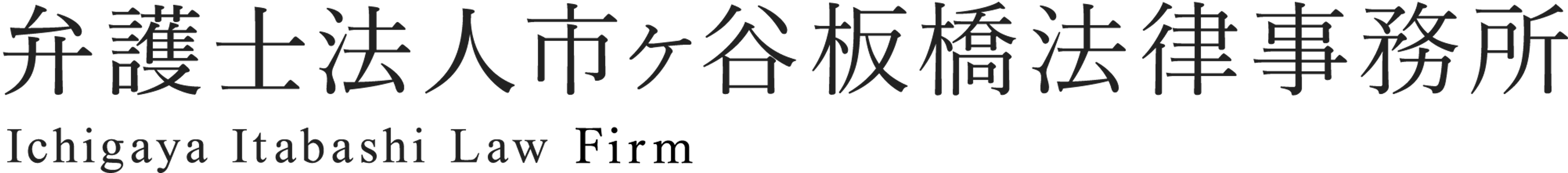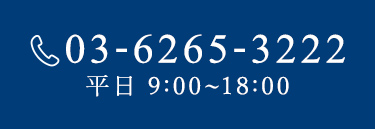休職発令をめぐる誤解と正しい対応方法
-人事担当者が押さえるべきポイント-
最終更新日:2025-08-26
「休んでいれば休職になる」は誤解
実務の現場では、次のような誤解が少なくありません。
- 長期間休めば自動的に休職になる
- 診断書の提出日をさかのぼって休職発令できる
しかし、これらは正しい理解ではありません。休職とは「会社が正式に命じること」によって初めて始まる制度です。単なる欠勤と、会社が発令した休職とは法的な位置付けが全く異なります。
発令日の曖昧さが大きなリスクに
「休職の開始日」が明確でないまま時間が経つと、次のような問題が噴出します。
- 「休職の発令を受けていないから退職処分は無効だ」
- 「開始日が異なるため休職期間の満了時期が違う」
こうした主張は裁判や労働審判で頻繁に争点となり、企業にとって大きな負担になります。
必要なのは「休職発令書」の交付
紛争を避けるために最も有効な方法は、休職発令を必ず書面で行うことです。具体的には「休職発令書」を作成し、従業員に交付・説明をしておく必要があります。
発令書には、少なくとも以下の内容を記載しておくと安心です。
- 休職の開始日と終了予定日
- 休職期間中の社会保険料の取り扱い
- 会社への連絡方法や担当窓口
- 復職の際の手続きや必要書類
書面で残すことにより、双方の認識が一致し、後々のトラブルを未然に防止できます。
弁護士に相談するメリット
休職制度は就業規則の定め方や運用の仕方で労使トラブルに直結します。万が一の紛争を避けるには、制度設計の段階から専門家の助言を得ることが効果的です。
- 自社の就業規則に沿った休職手続きになっているか確認できる
- トラブルを見越した発令書の文言を整備できる
- 紛争発生時のリスクや解決方法を事前に把握できる
「休職発令」を安易に考えてしまうと、後から対応が難しくなるケースが少なくありません。確実な手続きを行うためにも、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
ご相談のご案内
本記事は一般的な解説です。実際の対応は個別事情・就業規則等により異なります。休職制度の設計や発令書の整備、復職判定の運用まで、弊所が実情に合わせてサポートいたします。