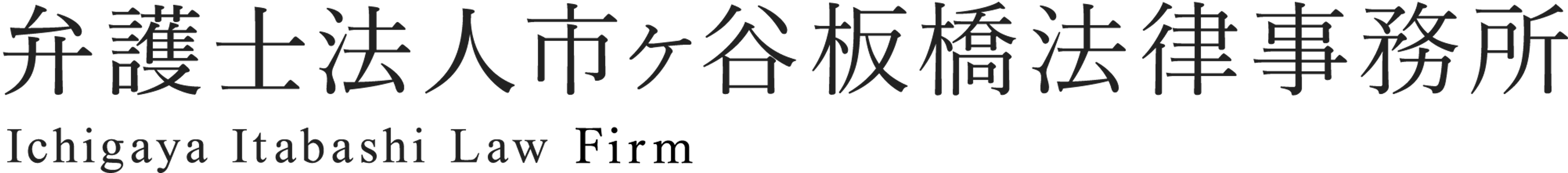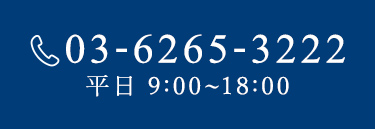2025/05/16 解決事例・コラム
【離婚】資産家の財産分与──高額資産だからこそ起きる離婚時のリスクと対応策
財産分与は、離婚時に避けては通れない大きな課題です。なかでも資産家や経営者など、いわゆる富裕層と呼ばれる方々のケースでは、共有財産の範囲や評価方法、分割方法が複雑化する傾向があります。

本コラムでは、当事務所が取り扱ってきた数多くの富裕層案件をもとに、一般のご家庭とは異なる「資産家特有の財産分与問題」と、その実務的な対応についてご紹介いたします。
資産の額・性質がもたらす複雑化
資産家世帯では、財産の種類が非常に多岐にわたるのが一般的です。株式・ストックオプション・ファンド持分・不動産・暗号資産(仮想通貨)・美術品・高級動産などが組み合わさっていることも少なくありません。これらはすべて一律に「現金」に換算できるものではなく、それぞれに特有の評価基準や換価可能性、税制上の取り扱いが存在します。
こうした資産を一つ一つ適切に評価し、公平に分与するには、高度な専門知識と実務対応力が求められます。
特有財産と共有財産の境界線
離婚時に問題となるのは、「どこまでが財産分与の対象になるか」です。一般に、婚姻前に保有していた財産や、個人で相続・贈与された財産は分与の対象外(=特有財産)とされます。
しかしながら、婚前に取得した資産であっても、婚姻中に運用益が発生している場合や、夫婦共有の資金と混在している場合には、分与対象と主張される可能性があります。とくに高額資産を保有する場合は、「この資産の原資はどこか?」「運用は誰が行ったか?」といった点を丁寧に整理しておく必要があります。
職業・能力と財産形成の関係
経営者や医師、スポーツ選手など、特殊な職業や技能を有する方の財産分与では、「財産は本人の努力によって形成されたものであり、必ずしも夫婦共有とは言えない」と主張されるケースがあります。
このような職業では、資産の多くが個人の能力や人的信用によって形成されており、その貢献度は他の職業とは比較にならない場合もあります。財産分与の際は、その形成背景を丁寧に主張し、2分の1ルールの適用を柔軟に見直すことが実務上有効です。
なお、2分の1ルールとは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産については、夫婦それぞれに平等な寄与があったと推定し、原則として折半するという考え方です。もっとも、これはあくまで「基準点」にすぎず、実際の分与割合は、財産形成への寄与度、職業上の特殊性、婚姻期間、家事育児の分担状況など、個別事情を考慮して修正されることがあります。
経営者・投資家ならではの分割の困難性
自社株や事業資産を所有している場合、それらが分与対象になったとしても、実際に現物を分け合うことは困難です。株式を他方配偶者に渡してしまうと、経営権が分散してしまい、事業継続に深刻な支障をきたす恐れもあります。
そのため、可能な限り「清算金方式」(株式等は維持したまま、現金相当額で調整)を用いるのが基本ですが、手元資金に限りがある場合は、分割払い、支払猶予、資産売却の検討など、柔軟な対応が求められます。
評価方法の選定が結果を左右する
保有資産が多様であるほど、財産の「評価方法」が結果を大きく左右します。
たとえば、ファンド持分やストックオプションなどは、表面的な数字だけでは本当の価値を測れません。将来価値、リスク、流動性、税制上の取扱いまで踏まえた精緻な評価が必要です。
評価誤差は数千万円単位の差を生むこともあり、経験豊富な専門家による評価レポートの取得は不可欠といえるでしょう。
対策は離婚前から始まっている
資産家の方ほど、離婚が現実のものとなる前に「万が一の備え」を講じておくことが重要です。たとえば婚前契約や婚後契約といった法的手段を講じておけば、離婚時の財産分与条件をあらかじめ明確にしておくことができます。
また、事業承継や資産管理の観点からも、離婚リスクを想定したファミリーガバナンスの整備は、重要な経営戦略の一つといえるでしょう。
最後に
資産家の離婚には、一般的な離婚では見られない複雑性とリスクが伴います。公平な財産分与を実現するためには、法的知識だけでなく、資産評価、税務、ファイナンスの知見も必要です。
当事務所では、富裕層の財産分与に精通した弁護士が、個別の資産分析から交渉戦略の立案まで、トータルでご支援いたします。「経済的な清算」が「精神的な清算」にもつながるよう、最善の解決をともに目指しましょう。
弊所では初回30分無料相談を実施しております。ぜひお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。